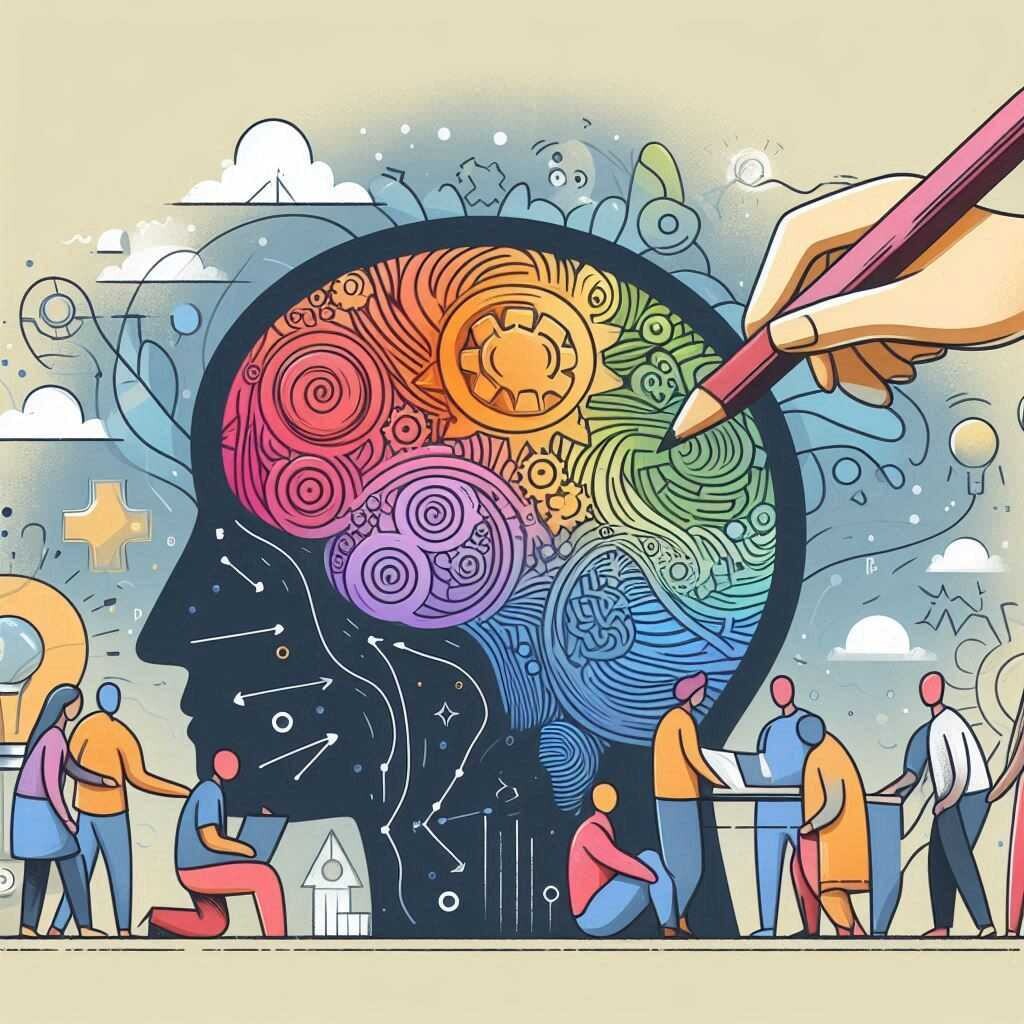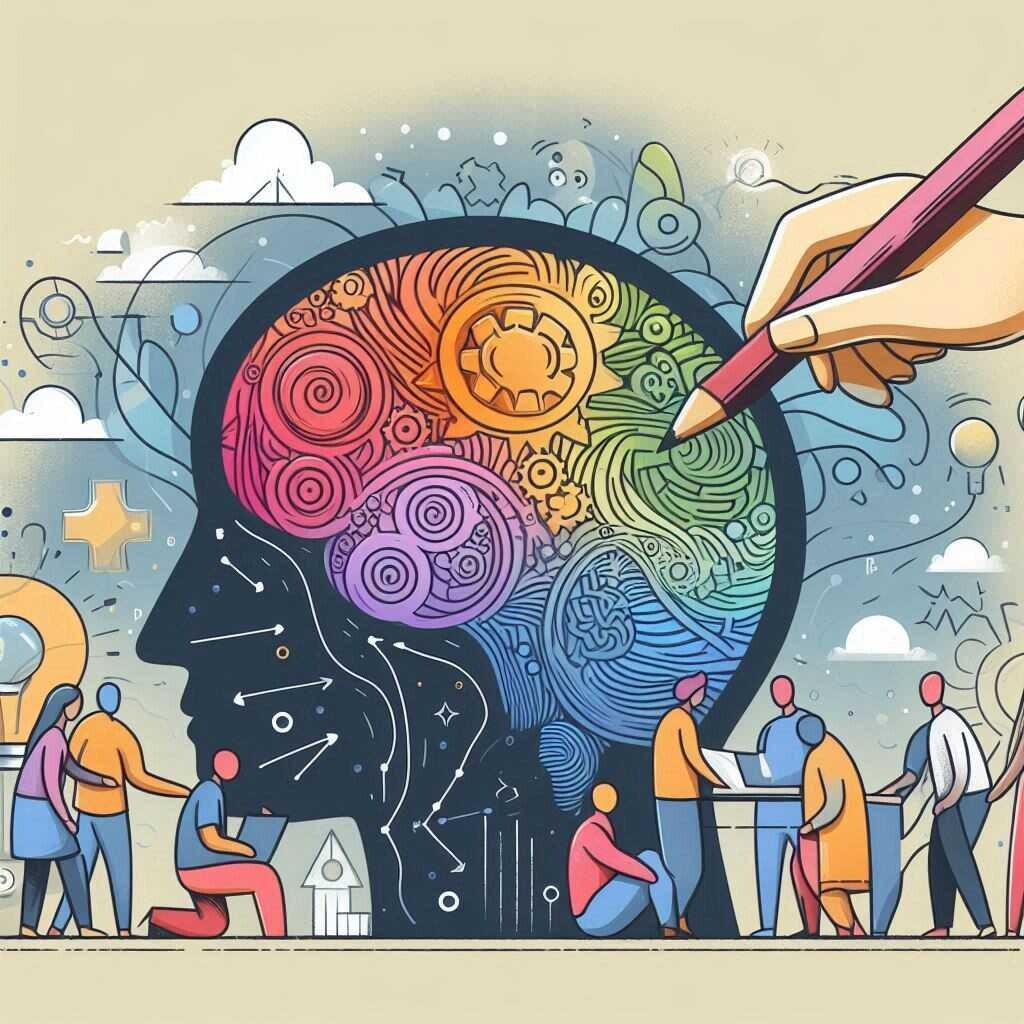堀正
心理学全般——中でも言語心理学、発達心理学、パーソナリティ心理学、精神分析、コミュニケーション論

心理学者、翻訳家。群馬大学名誉教授。
東京都立大学人文学部・大学院人文科学研究科(心理学専攻)博士課程単位取得。(財団法人)電気通信政策総合研究所研究員・主任研究員を経て、1992年から群馬大学教養部・社会情報学部助教授・教授。2013年4月、群馬大学名誉教授。
放送大学『人格心理学‘04』の「第10回 文化とパーソナリティ」を2008年度まで担当。2010年度群馬大学ベストティーチャー賞受賞。2015~2020まで放送大学群馬学習センター客員教員。現在、群馬県内の2つの看護学校で「発達心理学」の非常勤講師を続けている。
論文としては、「人間応援学(じんあいおうえんがく)ノススメ 」(『支援対話研究』第2号、2014)、「コーチング心理学の展望」(『群馬大学社会情報学部研究論集』第16巻、2009)、「“The Giving Tree”の各国語への翻訳から言語と文化を考える」(『群馬大学社会情報学部研究論集』第15巻、2008)、「Measures for Students with Disabilities and Measures against Sexual Harassment in National, Public and Private Universities of Japan」(『群馬大学社会情報学部研究論集』第6巻、1999)」)。
著書には、『コーチング心理学概論』(共編著、ナカニシヤ出版、2015)、「絵本を『投影法』的な自己分析に使う試み」(あいり出版、2011)、「文化とパーソナリティ」(放送大学教育振興会、2004)。
翻訳書には、『新版インターネットの心理学』(共訳、NTT出版、2018)、『コーチング心理学ハンドブック』(監修・監訳、金子書房、2011)、『病院におけるチャイルドライフ』(中央法規出版、2000)、『矛盾の研究』(フランス語、三和書房、1986)、『LSD―幻想世界への旅』(ドイツ語、新曜社、1984)、『パーソナリティ―心理学的解釈』(新曜社、1982)。
東京都立大学人文学部・大学院人文科学研究科(心理学専攻)博士課程単位取得。(財団法人)電気通信政策総合研究所研究員・主任研究員を経て、1992年から群馬大学教養部・社会情報学部助教授・教授。2013年4月、群馬大学名誉教授。
放送大学『人格心理学‘04』の「第10回 文化とパーソナリティ」を2008年度まで担当。2010年度群馬大学ベストティーチャー賞受賞。2015~2020まで放送大学群馬学習センター客員教員。現在、群馬県内の2つの看護学校で「発達心理学」の非常勤講師を続けている。
論文としては、「人間応援学(じんあいおうえんがく)ノススメ 」(『支援対話研究』第2号、2014)、「コーチング心理学の展望」(『群馬大学社会情報学部研究論集』第16巻、2009)、「“The Giving Tree”の各国語への翻訳から言語と文化を考える」(『群馬大学社会情報学部研究論集』第15巻、2008)、「Measures for Students with Disabilities and Measures against Sexual Harassment in National, Public and Private Universities of Japan」(『群馬大学社会情報学部研究論集』第6巻、1999)」)。
著書には、『コーチング心理学概論』(共編著、ナカニシヤ出版、2015)、「絵本を『投影法』的な自己分析に使う試み」(あいり出版、2011)、「文化とパーソナリティ」(放送大学教育振興会、2004)。
翻訳書には、『新版インターネットの心理学』(共訳、NTT出版、2018)、『コーチング心理学ハンドブック』(監修・監訳、金子書房、2011)、『病院におけるチャイルドライフ』(中央法規出版、2000)、『矛盾の研究』(フランス語、三和書房、1986)、『LSD―幻想世界への旅』(ドイツ語、新曜社、1984)、『パーソナリティ―心理学的解釈』(新曜社、1982)。
メッセージ
わたしは大学で心理学を専攻してから、一貫して心理学を教えています。
高校在学時、大学での進路を考えていたとき『心理学入門』を読み、浪人の後、東京都立大学で心理学を専攻し、それ以降50年以上にわたって非常勤講師、専任教員として心理学の分野で仕事をしています。
大学の専任教員になる前、(財団法人)電気通信政策総合研究所研究員・主任研究員として、6年間にわたって電気通信の社会学的な受託研究を行い、欧米各国の電気通信事情の現地調査に出かけました。
大学時代には、英語、ドイツ語、フランス語だけでなくラテン語も基礎を学び、大学院受験の心理学部生を相手に英語、ドイツ語、フランス語の勉強会を主宰していました。在学中は言語に興味を持ち、ヨーロッパや東南アジアの言語について、文法書と辞書を片手に学び続けました。そのおかげで、英語、ドイツ語、フランス語からの翻訳書を出版する機会にも恵まれました。
こうした経歴があったために、新設されることとなった群馬大学社会情報学部の専任教員に採用され、在職中は、専門の心理学ではなく、「パーソナルコミュニケーション研究室」という名前で、心理学に関連する研究領域についても、広く科目、ゼミで教えていました。
群馬県内には心理学を担当できる教員が少なかったこともあり、21年間の在職中に県内のほとんどの大学、専門学校で心理学を教えました。
大学で教えるようになってから、いろいろな科目の教員が複数人で講義を担当する必要性を考え続けていましたが、在職中、それはほとんどかないませんでした。
退職後は大学という壁がなくなり、少しは自由に教えられるようになり、放送大学群馬学習センターでは社会人の方たちに心理学概論や心理学実験を教え、また非常勤講師として県内の大学で英語も2年間担当しました。
それでも、心理学という枠にとらわれずに、他領域の研究者たちと交流したいという想いを持っていたとき、2024年に「ディセミネ」という学びを提供する取り組みを見つけ、講師として参画することになったのです。
心理学が誕生した年とされている1879年から数えて140年以上が経過しています。また、日々、日常生活においては人間行動をめぐるいろいろな出来事が起きています。けれども「心理学」の基礎の上にそうした問題を取り扱う機運はまだまだ一般的になっていないように感じています。
大学というある年齢範囲の学生が学ぶ閉じられた世界の科目から「心理学」を解き放って、誰もが楽しく学べる場を提供できると幸いです。
高校在学時、大学での進路を考えていたとき『心理学入門』を読み、浪人の後、東京都立大学で心理学を専攻し、それ以降50年以上にわたって非常勤講師、専任教員として心理学の分野で仕事をしています。
大学の専任教員になる前、(財団法人)電気通信政策総合研究所研究員・主任研究員として、6年間にわたって電気通信の社会学的な受託研究を行い、欧米各国の電気通信事情の現地調査に出かけました。
大学時代には、英語、ドイツ語、フランス語だけでなくラテン語も基礎を学び、大学院受験の心理学部生を相手に英語、ドイツ語、フランス語の勉強会を主宰していました。在学中は言語に興味を持ち、ヨーロッパや東南アジアの言語について、文法書と辞書を片手に学び続けました。そのおかげで、英語、ドイツ語、フランス語からの翻訳書を出版する機会にも恵まれました。
こうした経歴があったために、新設されることとなった群馬大学社会情報学部の専任教員に採用され、在職中は、専門の心理学ではなく、「パーソナルコミュニケーション研究室」という名前で、心理学に関連する研究領域についても、広く科目、ゼミで教えていました。
群馬県内には心理学を担当できる教員が少なかったこともあり、21年間の在職中に県内のほとんどの大学、専門学校で心理学を教えました。
大学で教えるようになってから、いろいろな科目の教員が複数人で講義を担当する必要性を考え続けていましたが、在職中、それはほとんどかないませんでした。
退職後は大学という壁がなくなり、少しは自由に教えられるようになり、放送大学群馬学習センターでは社会人の方たちに心理学概論や心理学実験を教え、また非常勤講師として県内の大学で英語も2年間担当しました。
それでも、心理学という枠にとらわれずに、他領域の研究者たちと交流したいという想いを持っていたとき、2024年に「ディセミネ」という学びを提供する取り組みを見つけ、講師として参画することになったのです。
心理学が誕生した年とされている1879年から数えて140年以上が経過しています。また、日々、日常生活においては人間行動をめぐるいろいろな出来事が起きています。けれども「心理学」の基礎の上にそうした問題を取り扱う機運はまだまだ一般的になっていないように感じています。
大学というある年齢範囲の学生が学ぶ閉じられた世界の科目から「心理学」を解き放って、誰もが楽しく学べる場を提供できると幸いです。