「ニューロダイバーシティ」から障害と多様性を考える——その当事者性に着目して
開講期間: 2025年11月4日 〜 2026年1月20日
隔週火曜日19:00-20:30
難易度: 中級※ 難易度についてはこちらを参照ください。
内容紹介
こうした特性を疑われる自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(AD/HD)、学習障害(LD)などの「発達障害」はここ20年ほどで医学・教育・福祉などの領域である程度知られる概念となりました。文部科学省の2022年の調査によれば「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒」の割合が8.8%だったと示されています(文部科学省、 2022)。文部科学省は、この調査が発達障害のある子供の割合を即座に示すものではないことに注意喚起していますが、実際には発達障害のある子供の割合を推測する一つの指標として理解されています。
日本における政策は、極論すればこうした発達障害の人々を早期に発見し、治療・支援する方向に向かっているといわれています。しかし、いつの世もこうした「政策による支援」からは零れ落ちる人々がいます。たとえば、大人になってから職場で苦労し、心療内科に行って診察を受けたら診断が下りた、という人々は少なくありません。それでは、そうした「零れ落ちた人々」は、生きづらさや社会的不利を自己責任論で片付けられ、難しい人生を強いられるしかないのでしょうか。
近年、発達障害のある人々に一種の希望を与えうる概念としてニューロダイバーシティ(neurodiversity)というものが紹介されています。これは、医学的には脳機能の欠損として考えられてきた発達障害を「脳機能の多様性」としてとらえる視座です。これに基づけば、発達障害の生きづらさは本人への医学的介入のみで「解決されなければならないもの」ではなく、社会的な環境調整によって緩和・解決されうるものと考えることもできます。要は、多様性としての尊重がなされれば、当事者の負の側面のみを見る傾向が弱まり、医学のみに頼らずとも社会参加の促進が可能になるともいえるのではと考えられます。
その一方で、このニューロダイバーシティ概念が実は社会運動の中から発生した概念であるという事実が日本では見落とされる傾向にあります。この概念は、1980〜1990年代に英語圏の自閉症当事者がインターネット上で自閉症特性を「多様性」として考え、neurodiversityと命名したことから始まったと言われています。このことを看過してニューロダイバーシティを産業界や教育界が用いた時、当事者の怒り・やるせなさ・そして世界への希望…そうした根本的な思想が骨抜きになってしまい、都合のいいように当事者が社会によって操作されるという状況が繰り返されることになる、という危惧が拭えません。
さらに、この概念を理解するにはかなり学際的な知識が必要になります。そもそも対象は精神医学上の特性ですが、その精神医学の基盤には精神分析学があります。そして、概念の社会実装や応用にあたっては、社会福祉学や経営学など実践学問の基盤を知る必要があります。さらに、ニューロダイバーシティは障害を社会・文化の観点から扱う比較的新しい学問である「障害学」の対象でもあることから、その基礎である社会学や文学理論などの知識もあると深い理解が可能です。本講座では、これらの知見に適宜触れていきます。
以上のことを踏まえて、本講座では「ニューロダイバーシティ」が何を対象としているのか(概念発生の理由)、どのようにしてこの概念が生まれたのか(概念の歴史)、日本や世界においていかに活用されうるのか(概念の応用)、といったことを学びます。
毎回の授業においては、講師が導入講義を行い、その後にディスカッションの時間を取ります。倫理的に差し支えない範囲で結構なので、可能ならばご自身の経験や意見を共有してみてください。本講座の講師は、可能な限り双方向性を重視しますので、その旨ご理解ください。ただし、人の話を聴くことに集中して知識を吸収したい、というニーズによる受講を妨げるものではありません。
いつの時代にも「流行語」があります。今の教育・福祉・さらに経営の世界での流行語の一つはこの「ニューロダイバーシティ」かもしれません。そうした「流行語」が、なんとなく格好をつけて使うための「流行語」に終わってはその概念の存在する意味はなく、概念を生み出した人々の思想を軽んじることにもなります。講師としては、ニューロダイバーシティの本質を一人でも多くの人々とともに考え、いわゆる「共生社会」の望ましい在り方を構想する契機にしたいと考えています。皆様のご参加をお待ちしております。
※受講者はアーカイブ(録画)の視聴が可能です。リアルタイムで授業に参加できない場合も見逃しなく受講できます。
※途中参加の場合も、全授業のアーカイブ動画をご覧いただけます。
※アーカイブ動画は、講座の受付終了から1年間視聴可能です。
◆受講の流れ◆
1. お申し込み↓
2. 開講&受講の決定
↓
3. リアルタイムで授業に参加/アーカイブを見る/クラスルームから資料にアクセス
◦リアルタイム授業への参加URLは、受講決定時に自動送信されるメールに記載されている他、クラスルーム(下記)、マイページ内「ダッシュボード」からもご確認いただけます。また、各授業日の2日または3日前にリマインダーメールをお送りいたします。
◦講師とのやりとりや資料の配付、講座に関する運営からのお知らせ等は、Google社が提供する学習管理アプリケーション「Googleクラスルーム」から行います。クラスルームにつきましては、受講決定時に別途招待メールが届きますので、そちらからご参加ください。
◦クラスルームの使い方についてはこちらをご覧ください。
◦アーカイブはマイページ内「受講状況」からご覧いただけるほか、本ページ下部の「授業スケジュール」およびクラスルームからもご覧いただけます。
◦ディセミネでの初回受講時に送られる招待メールを承認することで、Googleカレンダーと自動で同期が可能です。是非ともお使いください。
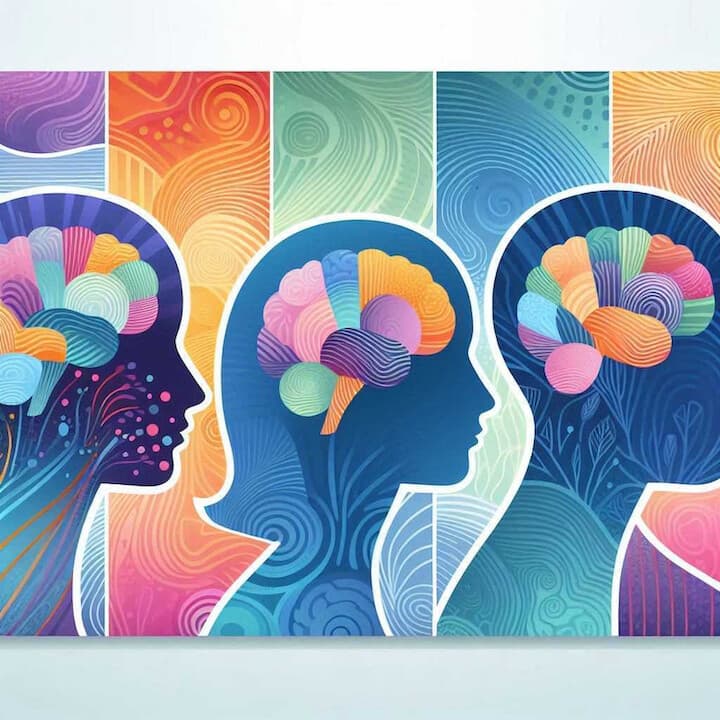
授業予定
ニューロダイバーシティの起源(歴史)
第2回 2025年11月18日(火)19:00〜20:30
ニューロダイバーシティの対象(精神医学的基盤)
第3回 2025年12月2日(火)19:00〜20:30
英語圏におけるニューロダイバーシティの議論
第4回 2025年12月16日(火)19:00〜20:30
ニューロダイバーシティと日本①(日本における導入)
第5回 2026年1月6日(火)19:00〜20:30
ニューロダイバーシティと日本②(日本における言説と議論)
第6回 2026年1月20日(火)19:00〜20:30
ニューロダイバーシティのこれから、授業のまとめ
※ 授業の進捗等により予定が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
こんな人におすすめ
発達障害に関わる学問(精神医学、教育学、社会福祉学、障害学など)を学んでいる人
ダイバーシティの意味を考え直したい人
講師情報

授業スケジュール
2025年11月4日 19:00 〜 20:30
第1回 ニューロダイバーシティの起源(歴史)
参加可能人数: 無制限2025年11月18日 19:00 〜 20:30
第2回 ニューロダイバーシティの対象(精神医学的基盤)
参加可能人数: 無制限2025年12月2日 19:00 〜 20:30
第3回 英語圏におけるニューロダイバーシティの議論
参加可能人数: 無制限次回開催
2025年12月16日 19:00 〜 20:30
第4回 ニューロダイバーシティと日本1(日本における導入)
参加可能人数: 無制限2026年1月6日 19:00 〜 20:30
第5回 ニューロダイバーシティと日本2(日本における言説と議論)
2026年1月20日 19:00 〜 20:30
第6回 ニューロダイバーシティのこれから、授業のまとめ
「ニューロダイバーシティ」から障害と多様性を考える——その当事者性に着目して
受講を申し込む